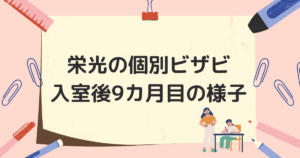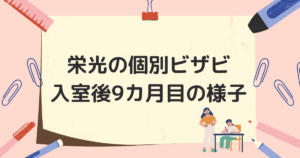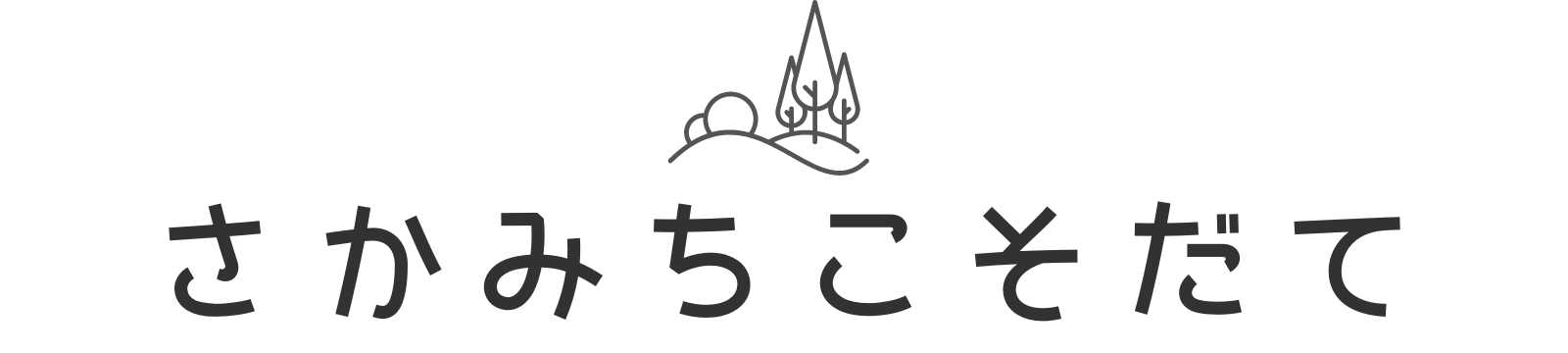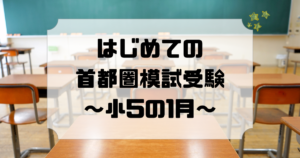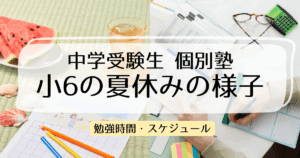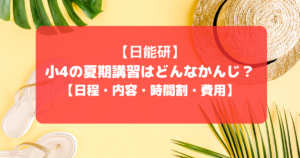aria
ariaいよいよ受験生の夏目前。これまでの様子を記録してみます。


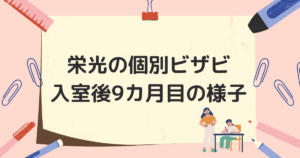
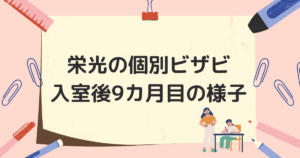
コマ数を増やし、算数を追い上げ
うちはまったく難関狙いではなく、2科目受験で、偏差値でいうと中~下を目指すゆる受験。(とはいえ本人は頑張っていますが)
塾に慣れ、通うことは順調にいっていましたが、算数の進度が5年生の冬時点で遅れていることが判明。
目標は6年生の夏休みまでに5年のテキストを終わらせること(6年のテキストは難関用なのでやらない)でしたが、今のペースだと追いつけないということになり、6年生になる2月から1コマ増やして、算数2コマ、国語1コマで進めることになりました。
本人も納得の上で、平日2日、土曜日1日の通塾。
そのかいがあり、6年生の夏休みの入り口くらいには、目標だった5年の算数テキストが終わりそうです。
6年の夏休みからは、「コンプリ」という総まとめに入っていくそう。
なんとか順調にこなしてもらいたいと願っています。
父が勉強を見る体制を確立
私は中学受験をしておらず、特に算数が大の苦手で、娘の勉強を見ることはできません。。
(国語なら見れるけど、国語は本人がほとんど解説を必要としてない)
算数に苦戦している娘さみなの勉強は父がべったりとくっついて教える体制になりました。
リモートで仕事している平日は、宿題のわからないところを解説する。
日曜日の午前中は二人でカフェへ行き、宿題と復習にあてる。
というサイクルが定着。
様子を見ていると、父の解説がなかったら、絶対受験無理だなと思います。。
算数の理解力は残念ながら私の脳みそが遺伝してしまったと感じます。でも、だからこそ受験勉強して算数の力をつけておくのって本当に良いなとも思います。
娘がやっている基礎的な受験算数って、就職のときのSPIとほぼ一緒。今身に着けておけばずっと役に立つなと思えます。
そんなこんなで、母はほとんど受験勉強にはノータッチ。。志望校を考えたりスケジュール組んだり送迎するというサポート役に徹しています。
個別のメリット、デメリット
日能研についていけなかった娘の選択肢としては個別しかありえませんでした。
個別は確かにメリットがあります。とにかく娘のペースに合わせてくれる。授業を休んでも振替れば進度に遅れは出ない。先生に質問しやすい。
娘には絶対に個別が合っています。
デメリットは他の子の様子が分からないことです。
日能研の、成績順に座らせる方式は正直嫌だなと思いますが、そうでなくても集団にいると嫌でも自分の成績の位置がわかるし、なにより他の子が頑張っている姿が、良くも悪くも刺激になると思います。
個別はそれがない。他の子がどれだけやっているのかがわからない。だから焦らない。
まあ、他人の一挙一動に心を乱される刺激的な環境にいられなかったからここにいるわけですが。
他の方の受験ブログを読むと、命削って頑張るくらいの気概でやっている方が多いので、うちは超激ゆる受験生だなと感じます。
志望校は決まった。でも火はついてない
5年生の頃は何校か文化祭には行きましたが、まだ成績がリアルになっていなかったこともあり参考程度にしていました。
6年生になる頃からは、現実的な偏差値で、狙う志望校を真剣に考え始め、学校見学にも行き始めました。
本人もそのころにはやっと受験するという自覚が芽生え、自分が通う学校ということを意識して見学に行っていました。
絞り込んだのは3校。滑り止め、現実ライン、少しだけチャレンジ校の3つです。どの学校も1時間以内、乗り換え1回以内で行けるところです。
最初に行ったのは滑り止めの女子校。
授業が特徴的で制服がかわいいこともあり、娘はとても気に入っていました。
2校目は校舎がとても綺麗な共学校。現実ラインの学校です。見学後は滑り止め校よりも良い印象を持っていました。
3校目はキリスト教の女子校。チャレンジ校です。
ここは一度、模試で来たことがあり、その時は娘はあまりピンときていない様子でしたが、見学した日に部活動の体験をさせてもらったのが相当楽しかったらしく、「ここを第一志望にする!」といきなり1位に躍り出ました。
夫はキリスト教の女子校にあまり良い印象を抱いていなかったようですが、見学で生徒と話した印象がものすごくよかったようで、「正直、一番通っているイメージがついた」と言っていて私が驚きました。
私はもともとこの学校が、通いやすいし良いなと思っていたので、本人と夫が気に入ってくれたのが嬉しかったです。
おそらくここからはもう志望校は変えることはありません。
どの学校に行っても良いと私は思っています。本人もそのようです。
ただ、まだ心に火がついて勉強している様子はありません。
よく聞くように、火が付くのは本番直前や、どこかに落ちた後。。なのかもしれないですね。
小さいころにもっとやらせておけばよかったのか?
勉強していく中で足かせになっているのが計算力です。
そこかよと思われるかもしれませんが、夫いわく、「計算でつまづくので考えるところに到達しない、公文やらせていればよかった」と。
しかし過去を思い返すと、娘はとても公文に通える状況ではありませんでした。
小1の行き渋り、習い事も体験だけで行かないことがほとんど。
学童すら嫌になり、母がリモートにして放課後を対応していました。
家で学校の宿題をつきっきりで見るのが精いっぱい。
そのころ公文に行かせようとしたとしても、絶対続かなかったと確信できます。




夫もそれは同意見。
「性格的にしょうがない。妹のたひなは、小1から公文に行かせてみたい」とのこと。
自身が公文で計算力がついたそうで、中学受験には有利になると考えているようです。
私も、行ってくれるに越したことはないと思います。
でも塾や習い事に行けるかどうか、続くかどうかは本当に個人差があります。
さみなは難しいタイプだった。だから今どうこう言ってもしょうがないのですよね。今、そしてこれから頑張るしかないです。
でも、勉強させることに関しては、私はもう少し「机に向かわせる」ことに取り組んでも良かったのかなと今になっては思います。
たくさんの育児本を読む中で私に刺さっていたのは「低学年までは思いっきり遊ばせろ、そうすれば後伸びする」という話でした。
保育園時代から低学年まで、机に向かう「お勉強」より「外遊び」「友達との遊び」を優先し、ストレスかけずに思いっきり遊ばせました。
で、結果「後伸び」したのか??
今のところしてません!
じゃあ、お勉強させていれば今、もっと成績は良かったのか?
わかりません。
「後伸び」っていつのこと指すのか???
わかりません。
小6?中学生?高校生?大学受験の時?就職するとき?社会人になってから?????
数多くの教育者が言うのはおそらく「中学受験直前の伸び」や「中学・高校に入ってからの伸び」などの学生時代の飛躍のことだと思います。
そしてもう一つ感じるのが、偏見かもですが「後伸び」ってわりと男子のことを指すほうが多いのではないか。
小さいころ思いっきりやんちゃに遊んでいた男の子が、中学受験や高校受験で一気に伸びる。そんなことを言っている印象を持ちます。
うちの子の外遊び、友達遊びは、勉強の出来に直結している印象は今のところありません。
でも学校内でリーダーシップを取ったり、自分の意見を言ったり、友達とうまく関係を築いたりすることにかけては、割と上手にできている感じがして、それは今までの友達との遊びやコミュニケーションの経験値が活きているんじゃないか。そんな気はしています。
主題からずれた話になった気もしますが、要は、「幼少期の過ごし方が勉強の出来に与える影響は、はっきりしたことはわからない」「子どもによって違う」です。
受験にまつわる2つのプチ事件
事件簿① 休講に気づかず塾へ
5年生の頃のことです。私が仕事中に珍しく塾から電話がかかってきました。
「担当の先生がインフルエンザで来れません。2コマあとだったら、別の先生が担当できるので、それでも良いですか?今日を逃すと他の日に振り替えるのが難しくて。。。」
私は、急な変更に対処できないさみなの様子が目に浮かび、本人と話してから決めたかったのですが、時間がないとのことで渋々了承しました。
急いでキッズケータイに「時間がずれたから、まだ家にいていいよ」とメール。
反応がないので何度も電話をかけましたが、一向に反応する気配なし。
GPSで所在地を確認すると、いつも通りの時間に塾に向かってる!!
このままだと、行っても先生はおらず、2コマ分待たないといけないという事実を塾ではじめて知らされることになる。
急な予定変更に1人で対応することが超苦手なさみな。
おそらく、帰る判断もできず、やるべき勉強のネタもなく、泣くのを必死でこらえているはず。。。。
退勤してやっと自宅の最寄り駅に着き、塾に電話すると
「塾に来て知ったようで、少し泣きそうになってました。今は自習室にいます」とのこと。
予想的中。。。
このまま一人で待たせて、いつもと違う先生の授業を受けることは精神的に耐えられないだろう、一回迎えに行って、食事したあとに戻らせよう。
そう考えて、妹のたひなを迎えに行ったあと、塾に行ってさみなをピックしました。



なんでケータイ見なかったのよ⁉



サイレントモードにしてた。。。
5年生のこの頃はまだ友達とケータイでやり取りすることも少なく、持ってても見てないことが多かったのです。
とりあえず塾の近くのレストランに入り、時間に間に合う簡単なメニューを注文。
「食べ終わったら塾行くんだよ」と言いながら注文を待っていましたが、すでに心が折れているさみな。ポロポロと泣きながら「塾行かない。。。」と言い、ごはんも全然食べません。
なんとか塾に間に合う時間に食事を終えて店を出ましたが、店を出たところでさみなは立ち尽くし、大号泣。
私はかわいそうだと思いつつ、これくらいのこと乗り越えてほしいという気持ちもあり、塾長に行くと言ったのにやっぱり行けませんと言わなくてはならないストレス(親がちゃんと対応できてないと思われる)もあり
「もう行くって言っちゃったんだから行って!」
「また今回みたいなことがあったときも行かないつもり⁉いつもそうするの⁉」とキツく問い詰め、「行け!」「行かない!」の押し問答。
暗くなったショッピングモール前の道端で泣きわめく子どもと激怒する親。。。
妹のたひなも、ただならぬ事態に泣き出す始末。。
はたから見たら軽く虐待です。。
結局、さみなの「絶対に振替するし、塾は辞めないで次は行くから」という懇願に私が根負けし、塾のビルを目の前に見ながら、電話で欠席の旨を伝え、帰宅しました。
翌日、妹のたひながピアノ教室で
「昨日大変だったんだ~。ねえねが塾行かないって言って、ママが怒ったの、道で」
と先生に正確に報告してました。
事件簿② 模試に行かない
数か月に一度行われる「首都圏模試」。
サピや日能研ではない塾のさみなはこの模試を受けることで成績判定をしていく大事な模試です。
事件は夏の首都圏模試で起こりました。
この日の模試は、前日に修学旅行から帰ってくるというスケジュール。
疲れているだろうけれど、疲れた状態で受ける実際の受験のリハーサルになるだろうから、朝早いけど頑張って受けに行こう。と約束してました。
修学旅行はとても楽しんで帰ってきたさみな。
「明日は模試だからね」と念を押したところ、
「わかってるよ。あっ会場〇〇校だ。(憧れの学校)わーい♪」
とのんきな様子。
大丈夫そうかなと思い、模試の後、会場近くの祖父母の家に行く予定を立て、眠りにつきました。
翌朝。
起きる時間に起こしても、起きません。
おかしいな、疲れてるのかな、と思いつつ何度も起こします。
起きません。
これは「行きたくないです強行突破」の再来です。
見ると枕に顔を押し当ててちょっと泣いてます。
この模試を逃したら、夏休みに模試の振り返りができません。それに、行かないことを許容して、祖父母の家に行って楽しむことはできません。
私はいつものごとく怒りがこみあげてきてしまい、泣いているさみなに向かって「疲れてるから行かないとかありえない!予定してたでしょ!行きなさい!」とガミガミ怒りました。
そこへ夫が来て、「まあまあ」と私を一度部屋から退出させます。
夫とさみなと二人で話をしましたが、やはり意思は変わらないようで、部屋にカギをかけて籠城状態に。
夫と私で「やはりか。。」とげんなりしつつ、
もし行かないのなら、楽しみにしていた祖父母の家訪問は無し。
二人で問い詰めると逃げ場がなくなるので、母だけ厳しい姿勢を取り、受験やめるか?という追及も交えてしっかり話す。
というスタンスにするとして、ギリギリまで部屋から出てくるのを待ちました。
泣きながら着替えをする様子がありましたが、結局そのまま部屋から出てこず、模試は断念。。
しばらくして、部屋から出てきたさみなに、私から静かに話をしました。
「疲れているから行かないというのはもうこれからは通用しない」
「今日は祖父母の家に行く予定も立てていてそれも無しになった。みんなの予定を振り回したことを認識して」
「やりたくないなら受験辞めるという選択肢もある。ただ高校受験で頑張らないといけないのは一緒。どうするのか良く考えて」
と伝えました。本人は静かに泣いてました。
その後、私が外出しているときにさみなと夫で話をし、その日は宿題をやり、受験は辞めず夏休み頑張る約束をしたそうです。
帰ったら笑顔で宿題してました。
先が思いやられますが、この子なりの成長を見守るしかないと改めて思った事件でした。
国語と算数の逆転現象⁉
読書大好きなさみなは、以前は国語のほうが圧倒的に得意だったのですが、
コツコツと算数を勉強していくうちに、いつのまにか算数が得意になってきた様子。
最近は漢字や文章作りのほうが苦手なんじゃないかと思うくらいになってきました。
算数は積み上げの教科なんだなとつくづく思います。
夏休み以降は国語にも力を入れて取り組まないとです。
夏休みの様子はまだ別記事で。